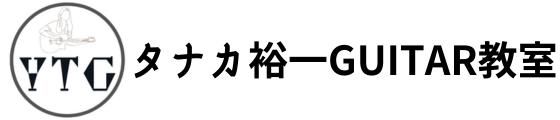ストラトでジャズは弾けない!?意外な理由をエレキギターの歴史から徹底解説!【1931年リッケンバッカー/ Frying Pan|1936年ギブソン/ES-150から】後編 JGT#76

体験レッスンのお申し込みはコチラから
ストラトでジャズは弾けない!?意外な理由をエレキギターの歴史から徹底解説!【1931年リッケンバッカー/ Frying Pan|1936年ギブソン/ES-150から】後編 JGT#76
ストラトでジャズは弾けない!?意外な理由をエレキギターの歴史から徹底解説!【1931年リッケンバッカー/ Frying Pan|1936年ギブソン/ES-150から】後編 #JGT76
はい!どうもこんにちはギターのタナカ裕一です。今回のテーマは以前から考察してきた「なぜストラトキャスターはジャズのイメージがないのか?」という疑問について、ハワイの歴史と音楽の繋がりを紐解きながら、深掘りしていきたいと思います。と、言うのが前回の内容。
今回はハワイの歴史と音楽の繋がりを経まして。「ストラトでジャズは弾けない!?意外な理由を『エレキギターの歴史』から徹底解説!」ということで、お話します。まだ前回の動画を見ていない方は、ぜひ前編からチェックしてみてください! 前編では「ハワイの歴史と音楽が、20世紀初頭のアメリカ音楽とどう繋がっていたか」について話しています。そちらを先に見てもらうと、より話の全体像が見えてくるかと思いますので、前編も併せてご覧ください。重要なポイントの振り返りもしますので、この後編から見ても大丈夫です。
今回の動画をご覧いただくことで、ストラトキャスターとジャズの関係について、意外な視点から理解が深まるはずです。
前編のコメント欄でも幾つか「ストラトでジャズ弾けますけどww」的な反応をいただいたのですが、もちろんその通りで、全く問題なく「ストラトでジャズ弾けます」し、ぼくの現在のフェイバリット・ジャズギタリストはニア・フェルダーと言うストラト使いで、実はこのギターにも彼のサインを貰ってます。自分自身数年間このギターをメインで使っていました。動画を通じてお伝えしたいことは「ストラトでジャズは弾けないよ」と言うことでは無く、「ストラトでジャズは弾けない」的なことが世間的に言われたりすることがありますが、それはいったいなぜだろう!?と言うことについて、ハワイの歴史、そして今回はエレキギターの開発史を通じて考察をしてみます。と言うことです。資料の写真なんかも沢山出てきますので、ぜひ最後までお楽しみください。
動画が始まる前に皆さまにお願いがございます。チャンネル登録を何卒よろしくお願いいたします。いつも応援ありがとうございます!皆さまのチャンネル登録が、より良い動画を作る励みになりますので。ぜひチャンネル登録、ご協力よろしくお願いいたします。
それでは行ってみましょう!
前回のおさらいと、エレキギターの黎明期
まず、前回のおさらい。前編の重要なポイントを5つ挙げておきましょう。
ここを押さえておけば、前編を見ていない方も以降楽しめます。
- ハワイが1898年にアメリカに併合され、1900年にアメリカの準州となるまでのいきさつ。西洋社会と繋がる前から存在していた「フラ」と言う伝統的な音楽を含む総合芸能が、アメリカナイズされて「ハパ・ハオレ」と言う、現在のわれわれがイメージするハワイアン音楽が生まれた。つまり、ハワイアンはハワイの音楽であると同時に、アメリカの音楽でもあるということです。
- また、ハワイアンはアメリカ音楽の他ジャンルにも大きな影響を与えました。例えば、ハワイアンの重要なサウンド、ラップトップスティールギター(膝や机などにギターを寝かせて、スライドバーを用いて演奏する)はカントリーなどでも使われますが、これはハワイアン音楽からアメリカ音楽への逆輸入だったりします。
- ハワイアンは、その他の当時流行していた音楽、ジャズ、カントリーなどと同じく1960年前後、あるいは1960年代半ばころまでアメリカの流行り音楽の中心にいました。
- しかし、1960年代半ば以降は、ハワイアンもジャズもカントリーも全盛期を過ぎて下火となり、ロックの時代へと移って行きます。
- ロックと言えばエレキギター!と言う感じですが、世界初のエレキギターは先ほどもお話したハワイアンギター、ラップトップスティールギターなんですね。1931年、アメリカ・ロサンゼルスのリッケンバッカー社が発売した「フライパン(Frying Pan)」こちらが世界初のエレキギターとされています。
ここまでが前回の内容。
なぜ最初のエレキギターがラップトップスティールギターだったのか?ようするに、1931年の「フライパン(Frying Pan)」発売当時、ハワイアン音楽がブームだった。ってことですよね。そう言うイメージが伝わっていればひとまずOKです🙆♀️
(画面:20世紀初頭のハワイアンブームを示すような当時のポスターや写真)
スパニッシュスタイル・エレキギターの登場
1931年のリッケンバッカー「フライパン」に続き、翌1932年には同社(当時はRo-Pat-In Corporationと言いました)から「スパニッシュスタイル」のエレキギターも登場します。(画面:リッケンバッカーの初期スパニッシュスタイル・エレキギターの画像)
ちなみに「スパニッシュスタイル」とは、私たちが普段目にする、普通に構えて弾くギターのことです。(画面:ラップスティールとスパニッシュスタイルの構え方の違いを示すイラストや写真) なぜわざわざそう呼ぶかというと、当時のアメリカではギターと言えばラップスティールギターの方が一般的で、それと区別するために「スパニッシュスタイル」と呼んでいたのです。
それほどハワイアン音楽とラップスティールギターが普及していた証拠ですね。(画面:当時の広告などでラップスティールが主流だったことがわかるような資料 ※任意)
そして1936年、ギブソン社がピックアップなどを改良した「ES-150」※エレクトリックスパニッシュ150ドルを発表します。(画面:ギブソン ES-150の鮮明な画像、様々な角度から) 楽器/アンプ/ケーブルのセットで約150ドル(2024年の3,400ドルに相当)
これが、商業的に初めて成功したスパニッシュスタイルのエレキギターとなりました。ES-150は、ジャズギタリストのチャーリー・クリスチャンが使用したことで一躍有名になり、(画面:チャーリー・クリスチャンの写真、ES-150を弾いている映像や写真) エレキギター、特にジャズにおけるエレキギターの可能性を大きく広げました。(画面:当時のジャズシーンにおけるES-150の存在感を示すようなイメージ)
フェンダー社の台頭とストラトキャスターの登場まで
ギブソン社が1936年にES-150を発売したころ、今回の本題、ストラトキャスターを作ったFender社は何をしていたかと言うと、創業者のレオ・フェンダーは1938年にラジオの修理会社『フェンダーズラジオサービス』を創業していました。ここに当時普及が進んでいたエレキギターのアンプ修理なんかが持ち込まれることがよくありまして、それで電気楽器行けるんちゃう!?と思ったんでしょうね。
1940年代に入ると、レオ・フェンダーはラジオから電気楽器に事業の舵を切って行きます。K&F manufacturing corporationを創業。1944年に取得した電動ピックアップ付きのラップトップスティールギターの特許を用いて、1945年にはハワイアンギター(ラップトップスティールギター)とアンプのセットを製造して、発売していました。新興企業です。
当時のアメリカではギターと言えばラップトップスティールギターだったと、先にもお話しましたが、ラジオ修理からキャリアをスタートした電気工作好きなレオ・フェンダーさんは楽器で言うとハワイアンブームに乗っかる形で、エレキギターもハワイアンギター(ラップトップスティールギター)から作りはじめたと言う訳です。
一方、同時期1940年代のギブソン社はスパニッシュスタイルのギターをエレクトリック化したES-150で、ジャズ界隈でシェアを得て行ったと。ここで少しギブソン社にも触れておくと、1894年に、ミシガン州カラマズーでマンドリン製作を開始し、1902年にその販売会社として、the Gibson Mandolin-Guitar Mfg. Co, Ltd.(マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド)を創業しています。ES-150が発売される1936年には、すでにマンドリンや、アーチトップギター(L5)のトップ企業となっていました。そう言う経緯もあって、ギブソン社のエレキギターはスパニッシュスタイルからはじまったと言うことです。
Fender社のエレキギターはラップトップスティールから始まっていますので、エレキギターに対する初期の方向性がこの2社の間でもう異なっていると言うのがわかります。
時代は進み、現在の主要なエレキギターが次々と発売されていきます。1950年にはフェンダー社から同社初のソリッドギター「エスクワイヤー」(後のテレキャスター)が登場。(画面:フェンダー・エスクワイヤー及びテレキャスターの画像) 1952年にはギブソン社がレス・ポール氏の名を冠した「レスポール」を発表します。(画面:ギブソン・レスポールの画像、レス・ポール氏の写真) そして1954年、フェンダー社から「ストラトキャスター」が発売されるのです。(画面:初代ストラトキャスターの画像、象徴的なショット)
ストラトキャスター開発のいきさつ
このストラトキャスターの開発で重要な役割を果たした人物がいます。ハワイ出身のデザイナーであり、エンジニア、そしてマルチ楽器奏者でもあったフレディ・タバレスです。(画面:フレディ・タバレスの写真、できればギターやウクレレを持っているもの) 彼は優れたミュージシャンで、『ルーニー・テューンズ』のテーマ曲でのペダルスティールギターの印象的なイントロや、(画面:ルーニー・テューンズのオープニング映像の一部) エルヴィス・プレスリーの『ブルー・ハワイ』でのウクレレ演奏などでも知られています。(画面:エルヴィス・プレスリー『ブルー・ハワイ』のジャケット写真や関連映像)
このフレディ・タバレスが、1953年にフェンダー社の創業者レオ・フェンダーのアシスタントエンジニアとして任命され、最初に取り組んだ大きな仕事の一つが、ストラトキャスターの開発でした。(画面:レオ・フェンダーとフレディ・タバレスが一緒に写っている写真があればベスト、なければそれぞれの写真)
ストラトキャスターに搭載された画期的な「シンクロナイズド・トレモロ」(いわゆるアーム)は、「ペダルスティールギターのようなサウンド」を出すことを目指して設計された、とも言われています。(画面:ストラトキャスターのトレモロユニットのアップ、ペダルスティールギターの演奏と比較するようなイメージ)
「言われています。」と言うのは明言されてはいないと言うことであって、レオ・フェンダーさんはハワイアンギター、ラップトップスティールギターから楽器を作り始めていますし、ストラトキャスター開発にあたっては、ハワイ出身のスティールギター奏者を招集していることなどから、1954年発売のストラトキャスターと言うギターはかなりハワイアン音楽が意識されていたであろうことは、客観的に見ても間違いないかと思います。
音楽の流行の変化とストラトキャスターの位置づけ
ストラトキャスターが1954年に発売され、それから数年も経つと、これは冒頭の前回の振り返り部分でもお話したように1960年前後と言った時代に突入していきますから、ハワイアン音楽、ジャズ、カントリーといった音楽ジャンルは全盛期を過ぎて、勢いを失っていきます(詳しくは前編をご覧ください)。(画面:ジャズやハワイアン音楽の全盛期の写真から、徐々にフェードアウトするような演出)
それに代わって台頭してきたのが、ロックンロールです。(画面:1960年代のロックンロールを象徴する映像、若者が踊る様子など) まさに1964年『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』の時代、ロックの時代の到来です。(画面:映画『~ヤァ!ヤァ!ヤァ!』のジャケット写真や映像クリップ)
ストラトキャスターは、その革新的な機能とサウンド、デザインによって、ロックミュージックを象徴するギターとしての地位を確立していきます。(画面:様々なロックギタリストがストラトを弾く象徴的な写真や映像をモンタージュ) 特に1966年以降ジミ・ヘンドリックスの使用は決定的でした。(画面:ジミ・ヘンドリックスがストラトキャスターを燃やす、歯で弾くなど、有名な写真や映像) 彼に代表されるような、シンクロナイズド・トレモロを使った過激なアーミング奏法は、ロックサウンドの重要な要素となりました。(画面:トレモロアームを激しく操作する映像のアップ)
これは次の話につながることで、触れておきますが、ジミヘンに代表されるような激しいシンクロナイズド・トレモロの操作、アーミングにはレオ・フェンダーさんはイラっとしていたと言うエピソードが残っています。要するにいわゆるロックな、音をギュワンギュワンさせるようなサウンドのために作られたものと言うことでは無かったと言うことです。
話はこのシンクロナイズド・トレモロ、アーム・バーにフォーカスしていきます。
トレモロアーム(ビブラートシステム)の歴史
ストラトキャスターのシンクロナイズド・トレモロ、アーム・バーについて歴史を少し遡ってみましょう。(画面:歴史を遡るような演出、年表風グラフィックなど)
実は、エレキギター登場以前から、弦楽器の音程を機械的に揺らす試みは存在しました。19世紀末から20世紀初頭にかけて、いくつかの機構が考案されています。(画面:古い発明品の設計図やイラスト) 先駆けとしては1891年ヴァン・デューセンが音を揺らす仕組みの特許を取得しています。1921年にはオーヴィル・ルイスがバイオリン用、1929年にはClayton Orr “Doc” Kauffmanがバンジョー用のデバイスを考案しました。
これらの装置の効果は音を揺らすビブラートでしたが何故か「トレモロ」と呼ばれていました。「トレモロ」と呼ばれた正確な理由は定かではありませんが、この初期の呼称が、後のフェンダーのシンクロナイズド・トレモロの名称にも影響した可能性があります。いずれにせよ、これらの試みは、音楽家が音に揺らぎを加える表現を求めていたことを示しています。(画面:音の揺らぎを表現する波形のようなグラフィック)
1930年代に入り、エレキギターが実用化されると、その表現力を高めるための専用システム開発が本格化します。その先駆けとなったのが、先ほど名前が出たClayton Orr “Doc” Kauffmanが発明した「Vibrola」(1929年出願、1932年特許取得)です。(画面:ドク・カウフマンの写真、Vibrolaの初期モデルの写真や特許図面)
これは現代のトレモロアームの「先祖」とも言えるシステムで、1930年代にエピフォンやリッケンバッカーのギターに搭載されました。(画面:Vibrolaが搭載されたエピフォンやリッケンバッカーのギターの写真)
Clayton Orr “Doc” Kauffmanは、このVibrolaを、当時人気のあったハワイアン・スティールギターのサウンドを普通のギターで模倣するために設計したと考えられています。(画面:スティールギターのサウンドを模倣するイメージ図や説明) これは、ギター用として特許取得された最初のビブラートシステムであり、エレキギターの表現可能性の初期段階を示す重要な発明です。しかし、Vibrolaにはピッチの戻りが不安定でチューニングが狂いやすいという欠点があり、技術的な完成度はまだ高くありませんでした。(画面:チューニングが狂う様子をコミカルに表現したイラストやアニメーション ※任意)
その後、1940年代後半にはポール・ビグスビーが、より安定性の高い「ビグスビー・ビブラート・テイルピース」(1953年特許)を開発。(画面:ポール・ビグスビーの写真、ビグスビーユニットのアップ、搭載されたギターの写真) これは特にホローボディのギターで人気を博し、現在でも広く使われています。(画面:グレッチなどビグスビー搭載ギター例)
そして1954年、レオ・フェンダーがストラトキャスターに搭載したのが、革新的な「シンクロナイズド・トレモロ」です。(画面:再度ストラトキャスターのシンクロナイズド・トレモロのアップ、内部構造の解説図など) これも実際にはビブラート効果を生むものですが、レオ・フェンダーが「トレモロ」と名付けたことで、「トレモロアーム」という呼称が一般化しました。このシステムは、従来のものより可動域が広く、安定性も向上しており、エレキギターの表現力を飛躍的に高めました。(画面:シンクロナイズド・トレモロのスムーズな動きを示す映像やアニメーション)
と言うのが、ストラト登場までのトレモロアームの歴史なのですが、時期的にことの起こりは19~20世紀にかけて、そしていまの形のトレモロアームの原型はClayton Orr “Doc” Kauffmanによるものだと言うのが重要事項。
そして、これまでの話がここからグッとまとまって行きます。
歴史の繋がり:カウフマンとフェンダー
レオ・フェンダーがキャリア初期にハワイアンギター(ラップスティール)とアンプの製造に注力していた「K&Fマニュファクチャリング」。(画面:K&Fのロゴや製品写真) この会社の「K」は、実は、先ほど登場したビブラートシステムの発明者、Clayton Orr “Doc” Kauffmanの頭文字、Kauffmanの”K”だったのです。(画面:カウフマンの写真と「K」の文字を強調) つまり、「K&F」はカウフマンとフェンダー(Fender)の会社でした。(画面:カウフマンとフェンダーの写真を並べて表示、「K&F」の文字を強調)
「K&F」の二人は、1944年電動ピックアップ付きのラップスティールギターの特許を取得し、1945年からアンプとのセット販売を開始しますが、翌1946年にカウフマンは会社を離れ、その後、現在の「フェンダー・エレクトリック・インストゥルメント・カンパニー」へと繋がっていきます。(画面:Fender社のロゴの変遷を示すようなイメージ)
重要なポイントを時系列で挙げて行くと。
・Clayton Orr “Doc” Kauffmanが1932年に特許を取得した発明品、ハワイアン・スティールギターのサウンドを普通のギターで模倣するために発明した、現代のトレモロアームの「先祖Vibrola」
・その「Vibrola」開発者Kauffmanと1940年ころタッグを組んで作ったものは1945年のエレクトリック・ハワイアンギター(ラップスティール)
・その後、カウフマンは会社を去りますが、社名をFender社に改め、1950年にはテレキャスターが発売。カントリー音楽などでシェアを得ます。
・1953年にハワイ出身のスティールギター奏者、フレディ・タバレスを招集し開発された、1954年発売、新型「シンクロナイズド・トレモロ」搭載のストラトキャスター
先にお話していた内容に、こうやってカウフマンのエピソードを加えるとさらに強く、レオ・フェンダー、そしてストラトキャスターとハワイアン音楽の繋がりが感じられます。
なぜストラトはジャズのイメージがないのか?考察の核心①
ストラトキャスターは、後に1966年以降ジミ・ヘンドリックスらによる(開発意図とは異なる)過激な「シンクロナイズド・トレモロ」の使用法などによって、ロックの代名詞となりました。(画面:ロックアイコンとしてのストラトキャスターの映像) しかし、ロックのイメージが定着する前、発売された1954年から1960年代半ばにかけてはどうだったのでしょうか?(画面:疑問符「?」のグラフィック)
Wikipediaのストラトキャスターの項目にはこう書かれています「1960年代半ばには人気が低下し使用するミュージシャンもほとんどおらず、製造中止も検討されていた」 (画面:人気が低迷している様子を示すグラフやイメージ、「製造中止も検討」のテロップ)
また、こうも書かれています「ストラトキャスターはテレキャスターと同様、本来はカントリー・ミュージックなどで使用することを想定して設計された。シンクロナイズド・トレモロ(後段で解説)も、カントリーやハワイアンで多用されるスティールギターのスライド奏法に近いサウンドを出すのが、本来の目的であった」とも記されています。(画面:カントリーで使われるテレキャスター、ハワイアンで使われるスティールギターの写真/映像)
まとめると、発売された1954年から1960年代半ばまでのストラトは、ハワイアン楽器のメーカーというイメージも強かったであろうフェンダー社製の、ハワイアン的なサウンドを意識したビブラートシステムを搭載したギミック楽器。ハワイアンのブームが下火になるのと共に消えて行く楽器、と言うイメージだった。そう言って過言ではないでしょう。
しかしストラトは、ジミヘンがいなければハワイアン音楽の下火と共に製造中止、消えて行く可能性のあった楽器だった。このことはかなり調べていて意外でした。
なぜストラトはジャズのイメージがないのか?考察の核心②
同時期に最盛期を迎え、その後ロックに人気の座を譲ることになるハワイアン音楽とジャズに話を戻しましょう。(画面:ジャズとハワイアン音楽の全盛期の写真や映像) これらの音楽と主要なソリッドギターの関係を見てみます。
- テレキャスター:原型となるエスクワイアは1950年から存在し、その「twangy」とも評されるシンプルで力強いサウンドから、カントリーミュージックの世界で早くから地位を確立。(画面:カントリーミュージシャンがテレキャスターを弾く映像) ジャズの文脈でも比較的早期から受け入れられていました。(画面:ジャズギタリストがテレキャスターを弾く写真) 古くはEd Bickert、ジョーパスがテレキャスを持った写真もあります。現在ではビルフリゼルやジュリアン・ラージなどがテレキャスターを使用するジャズギタリストです。
- レスポール:ジャズギタリストでもあるレス・ポール氏本人のシグネイチャーモデルであり、(画面:レス・ポール氏が自身のモデルを弾く写真) ジャズとの親和性は当初から高いものでした。(画面:ジャズギタリストがレスポールを弾く写真) アーチトップの形状や、搭載されたハムバッカーピックアップによる温かく太い音色と評されるように、ジャズと相性の良さそうなイメージがあります。レスポールを使用するジャズギタリストとしてはジョン・アバークロンビーなどが挙げられます。
- ストラトキャスター:これらと比較すると、ジャズと紐づくイメージはもとよりほとんどありません。そして、ジャズの世界では主流の楽器とはなりませんでした。(画面:テレ、レスポールとストラトを比較するグラフィック) ジャズの全盛期1930~1960年ころには、ストラトキャスターはまだ一般的な楽器としての市民権を得ておらず、それどころかハワイアンと共に消えかけていたのです。(画面:ジャズクラブのモノクロ写真の中に、ストラトが見当たらないようなイメージ)
仮に当時ストラトがジャズの現場で使われたケースがあったにせよ、その独特なサウンドやトレモロユニットから、「ハワイアン的なギミックを持つ楽器」というイメージが拭えなかったのかもしれません。(画面:ジャズマンがストラトのトレモロを訝しげに見る絵)
結論:歴史的なタイミングとイメージの問題
これらの背景を踏まえると、「ストラトでジャズは弾けない(似合わない)」という意見が出るのも、ある程度理解できる気がします。(画面:結論をまとめるテロップ表示開始) もちろん技術的には演奏可能ですが、「イメージ」の面では、
- 登場時期の遅さ:ジャズが最も隆盛を極めていた時期1930年代~1960年前後に、ストラトはまだどの音楽ジャンルにおいても「一般的な楽器」として確立していなかった。(画面:ジャズ全盛期とストラト登場時期を示す年表)
- 開発背景:ハワイアン音楽の影響(ラップスティール、フレディ・タバレス、トレモロの目的)が色濃く、もとよりジャズに特化した楽器ではない。(画面:開発背景のキーワード(ハワイ、ラップスティール、トレモロ)を示すアイコン)
- その後の経緯:ストラトキャスターは、ジミ・ヘンドリックスの使用による再評価。エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモアといったギタリストたちの使用により、ロックギターの象徴的存在へと登りつめます。(画面:クラプトン、ベック、ブラックモアがストラトを弾く象徴的な写真)ロック音楽の台頭と共に「ロックギターの象徴」というイメージが強烈に定着しました。(画面:ロックアイコンとしてのストラトの映像を再度強調)
これらの要因が「複合的」に絡み合い、ストラト発売の1954年から1960年代半ばまでの期間と、1960年代半ば以降はそれぞれ異なる理由ではありますが、とにもかくにも「ストラトとジャズが紐づくイメージ」が定着しなかったのではないでしょうか。(画面:ストラトとジャズの間に「?」マークが入るようなグラフィック) イメージが紐づいたのは当初の目論見ハワイアンですらなく、意図していなかった激しいロック音楽だった。
あるいはカントリー音楽や、一部のジャズ音楽におけるテレキャスターのように、ジャズの世界でストラトキャスターがスタンダードとなるための時間的な猶予がないまま、ロックの時代が到来してしまった、と言えるかもしれません。(画面:時間が足りなかったことを示す砂時計のようなイメージ ※任意)
結論「まとめ」
今回の内容をなるべく短くまとめると。
『1954年発売のストラトキャスターはおよそ鳴かず飛ばずのハワイアン向け不人気機種で、1960年代以降下火になるハワイアンと共に消えかかっていた。もちろん不人気機種なので、ジャズ界隈でも目立って使われることもなかった。その後、ジミ・ヘンドリックスの使用で再評価されるが、それはロックのギターとしてだった。ここまで話が出そろえば「ストラトでジャズは弾けない(似合わない)」という意見が出るのも、そりゃそうだ。と言う感じ。』
あるいは、単に時間が足らなかったとも言えるかもしれません。仮にジャズが1970年代まで全盛期を維持して、かつロック音楽の台頭が10年遅れていたら、もしかするとジャズ向けのソリッドギターと言えばストラト!と言うことになっていた世界線もあったかもしれません。ですが、それでもジャズ向け楽器としては先に浸透していたテレキャスターや、レスポールには及ばなかったかもしれませんけれども・・・。
そして、時代は変わり、現在では多くの優れたジャズギタリストがストラトキャスターを愛用し、その音楽的可能性を広げています。(画面:ニアフェルダー)
ストラトはとてもいいギターだと思います。ぼくにとってはシンクロナイズド・トレモロ用のバネが、アコースティックな響きをシミュレートするように感じる独特で、魅力的な楽器、まだまだ可能性のある楽器だと感じています。皆さんにとって、ストラトキャスターはどんなイメージのあるギターですか?この動画を見て、イメージが変わりましたでしょうか?ぜひコメント欄で教えてくださいね。
今回の考察が、皆さんのギターや音楽に対する見方を少しでも広げるきっかけになれば幸いです。(画面:様々なギターが並ぶ映像)
最後に
この動画が「面白かった」「役に立った」と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします!皆さんの反応が、今後の動画制作の大きな力になります。メンバーシップへのご参加や、スーパーチャットでの応援も心よりお待ちしております。
お相手はジャズギタリストのタナカ裕一でした。
ご視聴ありがとうございました。
それでは、また次回の動画でお会いしましょう!
体験レッスンのお申し込みはコチラから